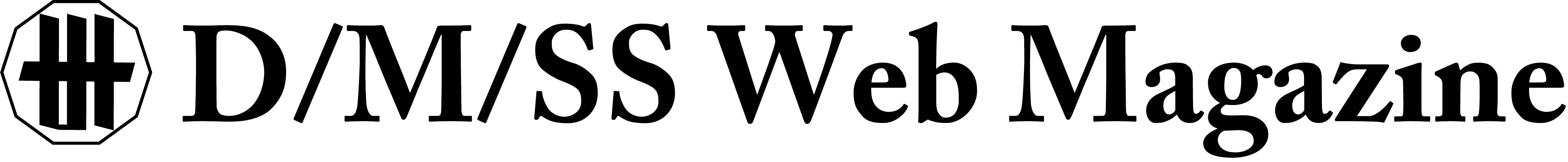「謎を解けと彼がいう――北村薫『雪月花――謎解き私小説』書評」
北村薫『雪月花――謎解き私小説』新潮社、2020年8月
手に取ったのは「謎解き私小説」という副題が引っ掛かったからだ。
日本ミステリ史における文学/非文学論争を蒸し返すつもりはない。文壇ギルドが解体したり崩壊して久しい現代において、「私小説」を名乗ることは過去以上の戦略を意味する。車谷長吉にしろ、西村賢太にしろタームを用いる意図がある。では、北村薫は何を意図したのか? それが本書の前で立ち止まったきっかけだった。
『雪月花』は視点人物である主人公の作家が、読んだ本・行き当たった出来事の中から惹かれた要素を起点として共通点をもつ人物や作品を辿り、時には人を頼りに資料へあたって思索を巡らしていく様子が描かれている。取り上げられる対象は多様で、ホームズ・シリーズのワトソン、『カルメン』、子供の頃に読んだ本、安藤信友の句、「何ひと」、中村真一郎を肝としつつ、付随して無数の人々と作品に言及される。
「考えているうちに、意図が繋がるように、思わぬところで、それとこれが結び付くのが面白い。」(p18)
「本と本は響きあうものだ。」(p186)
といった主人公の心境を形にした作品といえるだろう。
『雪月花』は謎の解決ではなく、謎を探求する過程に重きを置いている。これはロジックのことではなく、「謎を解釈する私の意識」のことである。「「私」の意識」を重視する立場は、一人称でありながら「私」という言葉の使用が少なく、謎を対して思索を巡らす場面の多くのページを割くという表現などにあらわれている。このような描写は、明治・大正期における自然主義文学的な「私」を客観化しようとする立場の上に成り立つものではない。厳密性とは距離をおく柔らかな筆致、およそ客体とは程遠い内面の生き生きとした動きは、私小説からの派生とされる志賀直哉らの心境小説に親和的であるといえるのであり、その意味で『雪月花』は形式的にも「私小説」である。
ネット上で『雪月花』の感想を眺めていると、ファンの多くが北村薫の既存の「エッセイ」との違いを掴みあぐねているという、興味深い傾向をみることができる。それほどまでに『雪月花』は「エッセイ」に近い空気を纏った作品だったのか、とあまり北村薫に触れたことのない私は間接的に教えられた。確かに「私」の表現を「エッセイ」とみるか「心境小説」とみるかは紙一重である。これは志賀直哉が心境小説と随筆に秀でていたことと無関係ではない。
しかしながら『雪月花』は緻密に計算された「小説」である。私がこの作品から「小説」性を強く感じるのは「謎解き私小説」という語に内蔵されたモードの要請が存在するからである。ここでいうモードとは鈴木登美『語られた自己』において抽出された、「作家=「私」(主人公)という前提」によって行われる読書スタイルのことである。端的にいえば「「私小説」というからには作者の事実を暴露的に書いているんだよね」という読者の認識である。文壇ギルドの時代から今日にまで通低する暗黙の約束は、逆にいえば「私小説」であると宣言をすることはモードを適用して作品を読んでもらえるということでもある。ここに作者の作為が滑り込む余地がある。
「自分のことをありのままに、少しも歪めず書けばそれでよい」と語ったとされる瀧井孝作を例外として、私小説を書くことをアイデンティティとする作家たちの多くは、事実をそのままに書いているわけではない。車谷長吉は「瀧井孝作が言うような嘘のない私小説は、基本的に面白くないのである。(中略)小説の醍醐味は嘘にあるのである。」(『文士の魂・文士の生魑魅』新潮文庫)といい、私小説にフィクションを織り込む重要性を語っている。藤枝静男があるがままにその瞬間の超現実的なイマジネーションを作中に投影したり、西村賢太が過去の私小説作家のパロディ的な要素を組み込むことで複雑な喜劇性を生んだことはその一例といっていい。「私小説」は読者には掴み得ない作家の事実とフィクションのせめぎ合いを楽しむものなのだ。
「作家というのは、一筋縄ではいかない。こんな事実を越え、書きたい真実を書くものだ。」(p58)
という作中の記述もある。
冒頭で言及した引っ掛かりはまさにこの点、北村薫は「私小説」をネタにして何をしようとしたのか、に帰結する。
北村薫が『雪月花』に込めた意図に対する私なりの解釈は、この文章そのものである。つまり、この作品には、読書を通じて一歩進んだ読み解くことの面白さを伝え、実際に『雪月花』という作品を読み解くことを促す、という構造を持っているのである。
『雪月花』の主人公は間テクスト性の様相を帯びた自由な解釈を披瀝し、度々わき道にそれては「閑話休題」を述べる。ロラン・バルト『表徴の帝国』や前田愛『文学テクスト入門』に通じる、「読むこと」の自由と可能性を教えてくれる本である。そこにあるのは「読者への挑戦」のように上から見下ろす著者と読者の戦いの場ではない。そばにいて滔々と関係の詩学を体感させ、読者を「読む」という行為に導いていく指南の場である。
読んでみたいという、読者の欲求の高まりには、続く謎が必要になるが、『雪月花』のどこに違和感を感じさせるキーワードがあるのか。それは看板にある「謎解き私小説」そのものである。
先で述べたように『雪月花』で用いられる「謎を解く「私」の意識」の表現は私小説の技法ともいえるのであり、その点では文字通り「謎解き私小説」の看板に偽りがないように見える。しかしながら、よくよく作中にちりばめられた要素に目を凝らすと、私小説とのズレに気づく。この作品には多くの作品と作家、出版関係者が登場するが私小説にアイデンティティを見出だした作家が登場しない。寧ろ、芥川龍之介や中村真一郎など私小説とは距離をおいた作家を取り上げている(芥川龍之介は晩年志賀直哉に傾倒し、変化した作風が葛西善蔵から評価されるに至るがそれも含んでいるのかもしれない?)。
特に最終章「はな」において多くの分量が割かれている中村真一郎には強い繋がりを感じる。中村が読売文学賞を受賞した『雲のゆき来』は、古典文学を読み解く主人公たる作家の心理と、巧妙に改変された史実の上に紡がれる今の時間の人間模様とを結びつけた作品で、構造が『雪月花』と似かよっている。
中村真一郎については作中で取り上げられた『四季』シリーズからみてもいい。『四季』は中村真一郎とも読める「私」の視点で描かれているが、前島良雄『中村真一郎回想』(河合文化教育研究所、2018年10月)では『春』を私小説と論じられた中村が怒りを露にする場面が描かれている。中村にとって『四季』シリーズは「私小説」とは異なる可能性を追求した作品だったことを示す象徴的な逸話であるといえよう。(前島の回想は『夏』が刊行された頃の話からはじまっており、中村が『夏』に書いた前島宛のサインも収録されている)
このように「謎解き私小説」と銘打ちながらも、構成要素は「私小説」から絶妙に距離を置こうとしているように見える。
閑話休題、と言いたくなるほど中村真一郎について考えが及んだところで、ふと気づく。この作品は「謎解き(をするように読者を誘導する)私小説」であると。北村薫は単に「エッセイ」的な小説を書いたのではない。綿密な計画によって、内容を楽しんだあとで、作品自体が装置となって作中の経験を自らの試してみることができる、二重の面白さを体験可能なギミックを内包する私小説を完成させたのである(泡坂妻夫の某作を思い起こすではないか)。北村薫のミステリ作家としての手腕を感じさせると同時に、表現技法としての「私小説」をエンターテインメントへと応用する挑戦として非常に興味深い。
『雪月花』の仕掛けに対して私は「謎解き私小説」をキーワードとして選択したが、読者それぞれに適した入り口があるように見える。おそらく「エッセイ」に馴染んだファンには既刊の内容とのズレなどを探るアプローチが可能だろうし、北村薫の本をはじめて手に取るという人でもワトソンの「H」をさらに深掘りすることもできるだろう(思えば絶対的な解決ではなく解釈を志向するこの作品はシャーロキアーナ的ともいえるし、高度な遊戯としてのニュアンスも内容に通じる)。
尚、本来であれば「謎解き私小説」の謎、は主人公のように北村薫の過去の著作にまで立ち返る必要があるが、そこまで踏み込むと一冊本の感想を越えるので、一旦立ち止まることにする。
この文章を書く過程で2020年11月に北村薫自身が『雪月花』を語るオンラインのトークイベントを行っていたと知った。もしかしたら、ここまで書いた内容はすべて語られているのかもしれない。けれども『雪月花』への感謝を込めて、要請された(と解釈した)二次創作を形に残しておくことにする。
written by XY生